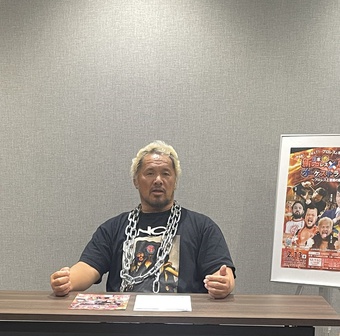HOME > SPECIAL INTERVIEW > 「諏訪内晶子」インタビュー

「諏訪内晶子」スペシャルインタビュー取材日:2014.09.02
チャイコフスキー国際コンクール史上最年少、
日本人初優勝という快挙を成し遂げてから20年余り。
世界を舞台に活躍を続け着実にキャリアを重ねてきた諏訪内晶子が今、
その精力を傾けているプロジェクトがあります。
昨年スタートした「国際音楽祭NIPPON」。
自身が芸術監督を務め、魅力的な企画を実現してきました。
この秋、開幕した第3回音楽祭では、
これから12月にかけて名古屋の各会場でもさまざまな公演が催されます。
演奏家としての枠を越え、芸術・音楽文化の発展のために
その手腕を発揮する彼女が、これまでの軌跡を振り返って今、思うこととは―。
今年で3回目を迎える国際音楽祭NIPPON。パーヴォ・ヤルヴィ氏率いるドイツ・カンマー・フィルハーモニー管弦楽団との共演は、目玉公演のひとつです。パーヴォ・ヤルヴィ氏とは長いお付き合いだとか。
初めて共演したのが1998年頃ですから、もう15年以上のお付き合いですね。パーヴォ・ヤルヴィさんというと思い出すのは、ヴァイオリンの弦。彼と一緒に演奏するときは、なぜか弦が切れるんですよ(笑)。初共演は大阪でしたが、そこでも切れました。そんな出会いでしたが、その後もお父様(指揮者ネーメ・ヤルヴィ)と共演したり、家族ぐるみのお付き合いをさせていただいています。そういう関係性もあって、舞台上ではいつも気兼ねなく演奏できますね。安心して演奏出来る体制を作ってくれますし。生のステージですから、演奏家はやはり緊張するときもあるんです。ご自身が弾かれない分、そういうときの演奏家のコンディションもよくわかるんでしょうね。その場の空気を、何も心配しなくてもいいように持って行ってくださるのは、やはり彼独特のものだと思います。
演奏に関してはいかがでしょう?
締め付け過ぎず緩過ぎず、というテンポ感が私のテンポにも合っていると思います。ソリストの演奏にオーケストラがぴったり付いてくださると、弾きづらいこともあります。ある程度、相互でいろいろな緩急の間がある方が演奏としては面白い。そういうことが、ごく普通に出来てしまうんです。彼と共演するときは、打ち合わせもほとんどしません。リハーサルの前に30分ぐらい演奏プランを語る指揮者もいますが、彼とは普通に「どうしてる?」という近況の話をするぐらい。それで「じゃ、舞台上で」と言って別れる。話し合う必要がないんですね。
何度か共演なさってきた中で信頼関係を築かれたからでしょうか?
最初からですね。ただやっぱり弾く前に、彼が向いている方向性が見える言葉をひとことくださいます。それで十分なんです。それが指揮者の仕事だと思っていらっしゃるのかもしれない。彼は凄いなと私が思うのは、音楽的なことはもちろんですが、非常に社交的なところ。例えばアメリカで共演したときなどは、DJの人と仲良くなって明け方までずっと話し込んでいました。「どうして?」と聞いたら、「それも僕の仕事のひとつ。せっかく時間があるのに、ひとりでぽつんといるというのは考えられない」と。全く違う分野の人とも長い時間、真剣に話し合ったりするんですよ。彼はエストニア出身で、まだ成人する前に家族5人でスーツケースを2~3個持って祖国を出てきたそうです。だから、自分にとって人間関係というのはとても大事なんだと。指揮者としても、それをとても大事になさっている方ですね。
今回は、メンデルスゾーンの「ヴァイオリン協奏曲ホ短調 op.64」を弾かれます。これまで、この曲での共演は?
ヤルヴィさんとは、パリ管弦楽団で一緒に演奏したことがあります。そのときも弦が切れまして(笑)。彼は目配せで「コンサートマスターから借りて」と。それで、さっと取り替えて演奏を続けました。終わったときは「あ、良かった。戻って」って、また目配せで。メンデルスゾーンのヴァイオリンコンチェルトは、三楽章が切れ目なく演奏されるので、終わるまでほとんど途切れることなく演奏するんです。だから緊張感があって、演奏家も客席も盛り上がります。ヤルヴィさんは、メリハリのある演奏を好むんですね。だから私も演奏中にギリギリまで間をたっぷり取ることが出来たりする。逆にそういうことを求める方なので面白い演奏が出来ますよね。付いてきて欲しいときはぴったり付けてくださいますし。共演者としては本当にやりやすい、出来ればもっと一緒に演奏したいという指揮者のうちのひとりですね。

諏訪内さんが感じられる、この曲の魅力を教えてください。
単一楽章のように続いているのは、当時としては画期的な協奏曲だったと思います。以前、この曲で共演したとき、ヤルヴィさんは「モルト・アパッショナートにね。」とおっしゃいましたが、もともとは「コン・フォーコ=火のように、情熱的に」という強い言葉が付いていた曲なんですね。つまりメンデルスゾーンは、そうしたことを望んでいたと思います。ロマン派の曲ですが、その中でも凄く煮えたぎるような感情というのがあるんじゃないかなと。とても聴きやすいメロディの名曲中の名曲ですが、その中にも煮えたぎるような感情のメロディが入っている。そこが魅力ですね。
現代作曲家への新しい作品の委嘱など、より広い視野で構築されているのがこの音楽祭の特徴だと思います。それは、留学先として音楽以外も学べるジュリアード音楽 院を選ばれたという、ご自身の10代の頃からの志向に通じますか?
アメリカに行く前、ヨーロッパで2ヵ月ほど演奏活動をしていたときもありました。それは素晴らしい体験でしたが、10代の自分にとってヨーロッパの歴史は重すぎて…もう少し自分の経験を豊かにするには、ある程度いろいろなこと対してオープンなアメリカの方がいいんじゃないかと思ったんです。それで、音楽だけでなく舞踊部門や演劇部門もあり、コロンビア大学とも提携しているジュリアードを選びました。その頃は、視野を広げたいというより、広げなければいけないだろうなと肌で感じていましたね。当時は、手当たり次第あるものを吸収しないといけないと思っていました。それはやはり、音楽家の家系に生まれた訳ではない自分が、急に表舞台に、それも国際的な舞台に立たされてしまったから。その舞台で活動を継続していくには、今のままでは絶対に無理だというのが自分でもわかっていて、どうしたらいいかということを考えての選択をしたのだと思います。
1990年、史上最年少でチャイコフスキーコンクール優勝。当時の日本では“諏訪内晶子ブーム”が沸き起こっていましたが、ご自身はとても冷静だったのですね。
そうならざるを得ないような、天地がひっくり返るような状況でしたから。私は優勝出来るなんて思って参加していなかったので、洋服も着たきりでした。当時はソ連でしたから、滞在中の食料を確保するのがまず大変なんです。本選まで1ヶ月分の食料をスーツケースに詰めていたので、持っていけるドレスは、予選・第二次予選・本選用に最低三着のドレスだけ。今では考えられないような時代でしたね。私は、本当はロシアに留学したかったんです。でも当時はルートが見つからず無理でしたから、チャイコフスキー国際コンクールに参加すれば憧れのロシアに行けると。人生には、いろいろな分岐点があると思いますが、そこに来たときに自分で選べるようになるには、やはりいろいろな経験が必要です。でもやっぱり、若いから勢いがあったんだと思います。コンクールに出ることについて「普通はしない選択だよ」と、周囲には反対されましたから。もし落ちたら、これまでのキャリアが台無しになるからって。
その後ジュリアードに進まれてからも、コロンビア大学で政治思想史を専攻したり、ベルリン芸術大学で学ばれたり、演奏活動以外にもさまざまな経験をなさいました。それらを経て、音楽や演奏に対するスタンスは変わってきましたか?
いろいろな経験をしながらも、やっぱり音楽のある生活を続けられて良かったなと思います。とても深いですし、音楽だけでは表現出来ないところもたくさんある。そういうものをいろいろな経験を通して身につけていったというか。「勉強しなくちゃいけない、何かしなくちゃいけない」じゃなくて、そういうベースがある人たちと接する機会がこれまでとても多かったので、それほど意識しなくてもよかったんですよね。演奏活動においては、経験や年齢を重ねて、自分のコンディションの調整をより丁寧に時間をかけて行うようになりました。演奏活動は表現することですから、終わって帰ったときにすべて出し切った状態になってしまいます。だから英気を養うことが大切。体の休め方や食事には、どこに行っても気をつけています。「たまには羽目をはずして」ということも、若い頃に比べて減ってきました。そうじゃないと体にこたえてしまう。それは仕事をしている身としては仕方がないですね。