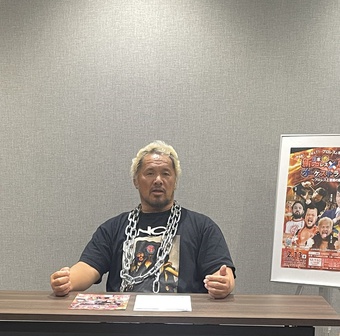HOME > SPECIAL INTERVIEW > 「平幹二朗」 スペシャルインタビュー
「平幹二朗」 スペシャルインタビュー取材日:2011.08.05

50年以上のキャリアを持つ大ベテランでありながら、
常に新しいジャンルの芝居や役柄に挑み続ける俳優、平幹二朗。
その意欲的でアグレッシブな仕事ぶりを支えているものは、何なのか。
長い俳優生活のスタートから現在までを振り返りながら、
自身の演技論や芝居への取り組み方について、大いに語ってもらいました。
俳優として50年以上のキャリアをお持ちですが、この世界に入られたきっかけはどのようなものだったのですか?
疎開先の広島で、たまたま演劇に関わったのが最初のきっかけです。通っていた高校が女学校と合併して、初めて演劇部というのができたんですが、女子の演劇部員しかいなかったんですよ。男子はそういう文化系の活動はしなかったんですね、田舎でしたから。僕は疎開してきた子供だったので何となく孤独だったから、目立ったのかもしれない。芝居に出てくれないかと言われて。背も高かったですしね。木下順二さんの「夕鶴」という戯曲の「与兵」という役をやって福山市の演劇コンクールに出場して優勝したんです。それが初めての演劇経験でした。けれども、それが俳優になろうということには繋がらなくて…。その頃、映画監督になりたいというのが将来の夢だったんですが、それには大学を出て助監督にならなきゃいけない。でも僕は理数系が全然ダメだったから大学は諦めて(笑)。たまたま演劇部にあった雑誌に俳優座養成所の記事が載っていたんですが、そこは数学がないんですよ、受験科目に(笑)。で、演出の勉強もできると思って、俳優座の演劇研究所を受験しました。普通、演劇学校に入ってきた人は大体、高校時代に演劇部で大活躍して入ってきたような人が多くて。でも僕は、楽に過ごせる学校に入れたという感じで、もうのんびり暮らしてたんですね(笑)。だから3年生になって卒業後のことを考えるようになって初めて、俳優座に残るのが一番いいのかなという気になって、少し一生懸命になったんですよ。それで運よく俳優座に残れて、それから何となく役がついたり、テレビのオーディションに行ったらいきなり主役に抜擢されて、それでNHKの芸術祭の奨励賞というのをもらったり…。そういう風に苦労なく俳優の道を歩み出してしまったんです。
俳優人生の転機になった演出家との出会い。
それから半世紀以上、さまざまな役を演じていらっしゃいますが、それらの魅力は、平さんご自身の魅力だと感じます。ご自身の人間性を役に投影させるということはあるのでしょうか?
当初も、俳優座で与えられる役柄には何かこう、自分の内面を反映できないと、もどかしく感じてはいたんです。おとなしい人畜無害のような役柄ばかり与えられていたので。自分としては激しい役をやりたいんだけれど、そういうタイプに見えないんですね。いろんな仕事をさせてもらいましたが、11年目でしたか、演出家の浅利慶太さんに「アンドロマック」という芝居に出ないかと言われて、初めて他社の作品に出演したんです。それで浅利さんに物言う術というか…一言ずつはっきり喋って、喋る目的はちゃんとしてなきゃいけないという、演技の設計図みたいなものを自分で作るという手ほどきを受けまして。そこで初めて、俳優の仕事って大変だなぁと思うのと同時に、面白いなと思いました。また、僕がやったのが激しい役だったので「こういう役がやりたかったんだよ」という感じがして、やっと俳優として面白いなぁと思うようになったんです。だから、すごい奥手なんですよ。11年ものんびりしてた(笑)。
浅利さんの演出によって、恐らくご自身も内面に持っていらっしゃる激しさを役に投影できたんですね。
そうですね。自分の内面を投影できるんだと知りました。それまで、自分の内面をぶつける役柄に出会えなかったもどかしさがあったんですが、初めて、自分の中の激しいもの、暗いもの、優しいもの…そういういろんなものを芝居の中に投影できる快感というんでしょうか、そういうものを感じられたんですね。それから芝居が面白くなって、やる気も出たってことなんですね(笑)。だから、それからの役作りとか、それはテレビや映画も含めてですけれど、結構、自分のいろんな面を投影するという作り方でやっています。
浅利慶太氏と7年、蜷川幸雄氏と30年。
ひとりの演出家と長く付き合うことで得たものとは。
脚本家や演出家が描いた役の人物像を崩さずに平さんご自身のスパイスを投影させるのは、とても繊細な作業ですよね。
僕は演出家に恵まれていたと思います。浅利さんと7年間、日生劇場でやった時代も、それほど摩擦というほどのものはありませんでした。「それは幹、違うんだよ。もうちょっと立派にやった方がいいんだよ」とか「そこは堂々とやれ」という風に言われて、僕がもうちょっとひねくれた演じ方をしようとすると「ダメだ!もっとストレートに立派にやれ!」とかね。実際にやってみれば、日生劇場の大きな空間の中で、特に現代劇ではなくて古典劇をやる場合に、そういうシンプルだけど力強い表現が必要なんだというのがだんだん分かりましたし、僕は納得してやれました。蜷川さんとは30年近く一緒にやりましたが、出会ったときは「もっとグチャグチャにやって」と言われて(笑)。僕もそういう風にやりたいなとも思っていたし、それで僕が考えていって違う展開をすると、彼ももっとそれに過激な音楽を使うとか、僕だけをクローズアップのライティングにするとか、いろんな演出的手法で、より開いてくれるんですよね。そういう意味で、みんな相性がよかった。そういう演出家に出会えたことが大きいと思いますね。それに、同じ人と長い間やったので、お互いの呼吸が分かりますから、どんどん違う演出家とやるよりは、ある時期集中的にひとりの演出家とやれたということは、お互いの力を広げていく面ではよかったんじゃないかと思います。ただ、あんまり長くやりすぎると、飽きが来ることがあるんですけど(笑)
キャリア50年以上を経た今、一作一作に込める思い。
現在、77歳でいらっしゃいますが、30代は浅利さんと、40代に蜷川さんとお仕事をされて、その後の50代、60代で、仕事に対する考え方に変化はありましたか?
50代から60代にかけては、僕個人の人生がいろいろ変動したので…離婚したり、子供と別れて暮らしたり、それから癌を患ったり…。そして、その癌のために蜷川さんと一緒に仕事をしなくなったり。キャリア一筋に上り詰めていこうとしていた自分を簡単に崩される出来事がいっぱい起こったんですね。だから、ひとつひとつ、いつ終わってもいいように、この一作一作を自分が納得できるやり方でやって、それができればまた次がある、という風に気持ちが変わってきました。だから70になったら、ホントに続けていることが幸せというか(笑)。いつまで続けられるか分からないので、ひとつの仕事を終えるとほっとして、まだ次も一応予定があるし「やれるな」という感じですけどね。30代~40代の駆け上がっているつもりのときは「自分はこんなに一生懸命やってるんだから周りもそれについて来てよ」という、ちょっと傲慢なところがあったように思うんですよね、失敗を許さないというか。だから、失敗した人の叱責の仕方なんかも容赦なかったと思います。「俺がこんなに努力してるのに、なんでしないの?」というような傲慢なところがあったんです。でも、60歳で癌になったりした後は、どんなに一生懸命やっても逆らえないものがあるんだから、「あんなに皆に厳しく当たってたのは、すごく傲慢だったな」と思いましたね。それから優しくなったって人に言われます(笑)。自分が思ってるほど完璧じゃない(笑)。だからそういう意味で、人との調和が少しうまくとれるようになったんじゃないかな。それまでは孤独癖だったので、自分が一生懸命やるっていうことだけが支えだったんですけれど。60になってやっと、人に支えられているんだ、ということが分かるようになりました。もっと早く、病気しないでわかるのが一番いいんですけど(笑)。
平幹二朗が新しい表現に挑む、次の一作。
この秋は舞台「エレジー ~父の夢は舞う~」に主演されます。「家族」「老い」「絆」など、とても今日的なテーマがデリケートに描かれている作品ですが、平さんが演じられる「平吉」という人物をどのように演じてみたいと思われていますか。
平吉というのは、偏屈で頑固な男なんです。息子が出て行ってからはひとり暮らし。僕も子どもはいますけど、今は一緒に暮らしているわけではないので、孤独に生きてることに慣れ過ぎているんですよね、自分自身が。今度の芝居は、どこか孤独な家族でもない家族のような5人が、傷を舐め合ったり、傷つけ合ったりしながら、定かでないものを求めて生きていく、というような話です。激しくぶつかり合うのではないので、そこが難しいと思うんですね。心の中は激しいと思うので、静かに見える人間関係でも食い違ってるものがいっぱいあるはずだから。決して古典劇のような激しさでは表現しませんからね。現代劇ですし。「エレジー」というタイトルのように、人生の終わりに向かっている男の周りに起こる話なので、悲劇性は大きいけれども生活感があり、淡々としていながら悲哀に満ちた人生のポエジーが感じられるような芝居になればいいなと思うんですね。決して重く激しいものではなくて、しみじみ観られて、でも悲哀感が残るような、そういう芝居にできればいいなと思っているので、僕が今までやったことがないような演技が求められるような気がするんです。「激しくやるのなら任せといて」という感じなんですけど(笑)。中に流れてるものは激しい思いなんだけれども、表に表現されるものは夕方の空のようなある静けさをもったものなので、その辺は「初めまして」という感じの演技なんですよ。だからちょっと僕には難しいなぁ、と今思ってるところです。自分の内面を投影するには、僕はちょっと内面が激しすぎる(笑)。
今回の可児市文化創造センターalaの公演では「アーチスト・イン・レジデンス」というスタイルで制作が進めされます。キャストとスタッフが可児市に滞在しながら稽古や作品づくりを行っていくということですが。
僕は家族を持っている頃も、役づくりとか家での芝居の準備なんかは閉じこもってやっていたんですよ、家族を遠ざけて。自分を苦しめて、自分の中に芝居の根っこを探すタイプなんです。蜷川さんとやってる芝居も激しい悲劇的なものが多かったので、日常生活からパッと切り離せないんですよね。稽古の段階では、楽しい家庭生活をしてきて稽古場に行ったら急に悲劇を演じることができないんですよ。だから結婚してる頃も、台詞を覚えるときや役を作っているときはなるべく自分の部屋やホテルに籠ったりして雑音を入れないようにしていたので、共同生活というのがすごく苦手なんです。一番苦手なことを強いられてるんで、さてどうやって耐えていけるか、それを乗り越えられるか、というのが大きな課題なんですね。この共同生活で、いい人にはいくらでもなれるんですよ。でもいい人になることは自分の役作りを邪魔する面があると思うので、悪い人になるかな(笑)。大体、僕はエゴイスティックな役者なんです。俳優座を辞めてから劇団に属さないのは、劇団生活が似合わないっていうことがよくわかったんだね、自分で。ひとりでなきゃいけないっていうこと(笑)。今回の芝居づくりは、一番辛い試練ですよ。だからその試練を耐えることに楽しみを見つけようと思ってます(笑)。